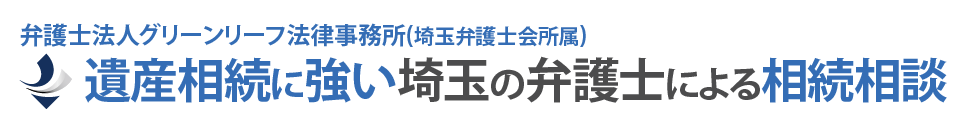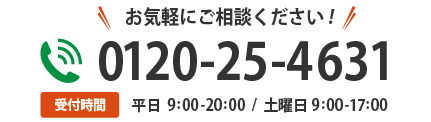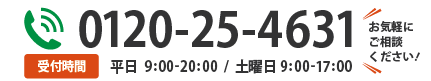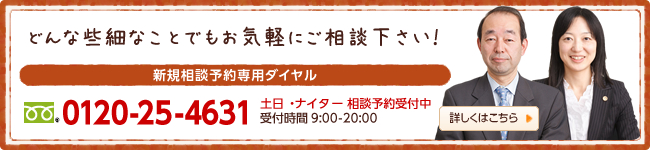ある日突然、見知らぬ土地の市役所から「相続人代表者指定届」を記入してくださいとお手紙が届いた――こんな経験をされた方もいらっしゃるのではないでしょうか? この記事では、「相続人代表者指定届」の意味合いや返信する際の注意点などを解説します。
「相続人代表者指定届」が届いた!

冒頭でもお話したように、ある日突然、見知らぬ土地の市役所等から、「相続人代表者指定届」(※自治体によって呼称が異なる場合もあります。)が送られてきて、期限までに記入して返信してください、と書かれていることがあります。
役所から突然、聞き慣れないタイトルの書類が届くことで、とても不安に思われるのではないでしょうか。
あるいは、役所からの手紙だからということで、反射的に記入して返信してしまう、ということもあるかもしれません。
しかしながら、この記事で解説するように、場合によっては、記入して返信しない方が良いというケースもあります。
したがって、まずは一呼吸おいて、冷静に状況を整理するところから始めましょう。
「相続人代表者指定届」とは?

「相続人代表者指定届」とは、不動産(土地・建物)の所有者が亡くなった場合に、その不動産が所在する市区町村役場から、亡くなった方の相続人宛てに送付される書類です。
書類と同封されてくるお手紙には、ざっくりと言えば、「不動産を所有していた○○さんが亡くなったので、○○さんの相続人に固定資産税等の納税義務があります。納税通知書を送る宛先を決めたいので、相続人代表者指定届を記入して返信してください。返信頂けない場合には、役所が決めた△△さんを相続人代表者とします。」というようなことが書いてあることでしょう。
そう、このお手紙に、重要なことがいくつも書いてあるのです。
まず、所有者が亡くなった場合の固定資産税について少しだけ解説します。
そもそも固定資産税は、その年の1月1日に不動産を所有していた人に課される税金です。
亡くなった人がすべて支払っていればいいのですが、滞納分や未納分がある場合には、その相続人が、相続債務としてこれを引き継ぐことになります。
それだけではありません。
1月1日時点で、「すでに亡くなっている人」が不動産の所有名義人となっている場合には、その相続人全員が、不動産を共有しているとして(※遺産分割協議が整うまでは、遺産は相続人の共有となります。)、固定資産税の納税義務者となります。
ちなみに、相続人が複数いる場合でも、ひとりひとりが、自治体に対して、全額の固定資産税を支払わなければならないことになっています。頭割りされるわけではないということですね。
そういうわけで、相続が発生しているけれども名義が変更されていない不動産が存在する場合には、市区町村としては、相続人の誰かに固定資産税等を支払ってもらう必要があるわけです。
しかし、納税通知書を全員に送付するとなると、コストや事務・管理の手間もかかりますし、二重・三重払いの危険もあり、いろいろ上手くありません。
そこで、市区町村は、相続人に対して、「固定資産税等の納税通知書を送る宛先を指定してほしい」すなわち「相続人代表者」を「指定」する「届」けをしてほしい、というわけで、この「相続人代表者指定届」の提出を求めてくるというわけです。
「相続人代表者指定届」を返信する前に考えること

次に、このお手紙を受け取った場合に考えるべきことをお話します。
市区町村からのお手紙には、おそらくどこかに「誰が亡くなったか」というのが書いてあるはずです。
まずはそのお名前を確認しましょう。
どうでしょうか。お心当たりのある方でしょうか。
市区町村は、戸籍等を調べて、その亡くなった方(被相続人)の相続人に対してこの手紙を送ります。
もし、先順位の相続人がいて、この人たちが相続放棄をした場合には、次の順位の相続人らに随時送られてくることになります。
そのため、このお手紙が届いたということは、ご自身が、その亡くなった方の相続人になっている可能性が極めて高い、ということになります。
したがって、このお手紙を受け取った方が、「相続人代表者指定届」を返信する前に考えなければならないのは、その亡くなった方の相続を承認するか否か、ということになります。
「相続人代表者指定届」を返信すると、相続放棄ができない可能性が高くなる
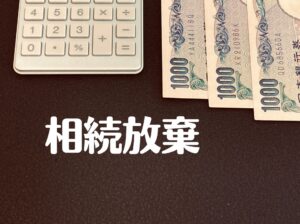
これがどういうことかというと、相続が生じた場合、相続人は、被相続人が亡くなったこと及び自身が相続人であることを知ったときから3か月以内に、相続放棄するか否かを決めて、放棄をする場合は手続きをしなければなりません。
しかし、たとえこの期間内であっても、相続の「承認」をした場合には、もはや相続放棄をすることはできません。
この「承認」に当たる行為、みなされる行為はいくつかありますが、「私が相続人の代表者として固定資産税の納税通知書を受け取ります」と表明することになる「相続人代表者指定届」の返信は、相続人であることの自認の表明であり、まさに相続の「承認」であると解釈される可能性は高いように思われます。
そのため、「相続人代表者指定届」を返信してしまうと、もはやあとには引けず、相続するほかなくなってしまう(相続放棄することができなくなってしまう)可能性が高いのです。
したがって、相続人代表者指定届の返信「前」に、相続を承認するか、それとも相続放棄をするか、検討する必要があります。
「相続人代表者指定届」が届くパターン別の対応

この「相続人代表者指定届」が届く背景には、前にも述べたとおり、相続登記が未了の不動産があるという事実があります。
そして、こういった状態が生じるパターンは、大きく2つに分けられます。
以下では、パターン別に、対応を検討します。
①遺産分割協議(調停等)が長引いている場合、あるいは放置されている場合

相続人同士での話し合いがまとまらず、遺産分割協議が長引いていて、結果的に相続登記ができていない場合には、すでに相続放棄ができる段階は過ぎていますから、相続人全員が納税義務者となります。
また、逆に、遺産の中に例えば「負」動産があって誰も積極的に関わろうとしないような場合、相続人同士でコミュニケーションをとることが難しく遺産分割協議がされてこなかった場合など、遺産分割自体が放置されてきたというパターンもあるでしょう。
この場合にも、すでに相続放棄ができる段階は過ぎていますから、相続人全員が納税義務者となります。
こういったパターンでは、どなたかが納税通知書の送付先となり(相続人代表者として届出をして)、固定資産税の負担方法を相続人で話し合う必要があります。
実務では、遺産分割協議中の固定資産税については相続人で頭割りして負担をしたり、最終的に遺産から清算するということが多いように思います。
②知らない親族、疎遠な親族が被相続人である場合

「相続人代表者指定届」が来て驚いた、という方の中では、このパターンが最も多いのではないでしょうか。
名前や存在しか知らず全く交流のない親族、そもそも本当に存在すら知らない親族が被相続人であるということもあります。
この場合には、自身が相続人であることはおろか、被相続人の死亡すら知らないことがほとんどではないでしょうか。
被相続人の死亡すら知らなかった、自分が相続人になっている相続があるとは全く知らなかった、という場合には、このお手紙を受け取った時点から、3か月以内に相続放棄の手続きをするかどうか決断しなければなりません。
したがって、「相続人代表者指定届」の返信には慎重になった方がよいでしょう。
そして、このパターンの場合、被相続人の経済状況について、全く情報が無いことが多いと思われます。
分かっているのは、被相続人名義の不動産が存在するということだけです。
他にどんな遺産があるのか、不動産の価値はどれほどなのか、借金があるのかどうか、公租公課(税金等のことです)の滞納がどれだけあるのかなど、不明な点が多いはずです。
ここで取りうる方針は2つです。
ひとつは、遺産の調査をして、相続を承認する(承認する可能性がある)方向で動くこと。
しかし、これはかなりリスクが伴います。上記でも述べたとおり、その経済状況や為人が分からないのですから、調べるのにも限界があります。例えば、被相続人に、業者ではなく個人間でのお金の貸し借りがあった場合や、何かの保証人になっていたなどの事情があったとしても、これを調べる術は無いといっても過言ではありません。
もしこの方針を取る場合には、少なくとも時間がかかります。まず、家庭裁判所に熟慮期間伸長の申立の手続きをとるようにしてください。
もうひとつは、相続放棄してしまうことです。
相続放棄をした場合、もしかしたらプラスの財産を受け取れたかもしれない可能性を手放すことにはなりますが、遺産を調査する人的・時間的・経済的コストはかけずに済みますし、万が一、借金などがあったとしても、請求されないで済みます。
このパターンのお客様がよくおっしゃられるのは「そもそも知らない人の遺産なんか当てにしていない。無くても困らない。面倒を持ち込まれる方が困る」というものです。これもひとつの賢明なご判断だと思います。
相続放棄をする場合には、「相続人代表者指定届」は返信せず、家庭裁判所で相続放棄の手続きを取るようにしてください。
市区町村には、あらかじめ(電話などで良いと思います。)、「相続放棄の手続きをするので、届けは提出しません」と伝えておくと丁寧でしょう。
無事に相続放棄の手続きが済んだら、家庭裁判所から「相続放棄申述受理通知書」という書類がもらえます。
これをコピーして市区町村に送れば、以後は相続人から外して扱ってもらえるはずです(自治体によって必要とする書類が異なる場合がありますのでご確認下さい。)。
まとめ

いかがだったでしょうか。
役所からの書類だからといって「相続人代表者指定届」を漫然と記入・返信してしまうことにリスクがあることはご理解頂けたと思います。
そして、実際のケースとして、全く交流のない(存在すら知らない)親族の相続人であるとして、市区町村から手紙が届いたという場合も少なくありません。
こういった場合には「相続放棄」という選択肢があることを念頭に、慎重にご対応いただければと思います。
もし、ご自分で対応するのが難しかったり、ご不安な点、疑問点を解決したいという場合には、ぜひ一度弁護士までご相談ください。
現在のご状況の解説と、これから取りうる方針について、法的なアドバイスが可能と思います。
また、弁護士に相続放棄等の手続きを任せたいとなれば、ご依頼することも可能かと思います。
一人で悩まず、即断せず、一度お話頂ければ幸いです。
グリーンリーフ法律事務所は、設立以来35年以上の実績があり、18名の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。
また、各分野について専門チームを設けており、ご依頼を受けた場合は、専門チームの弁護士が担当します。まずは、一度お気軽にご相談ください。