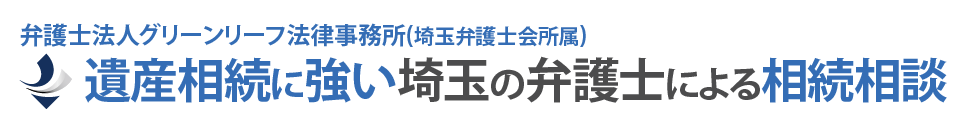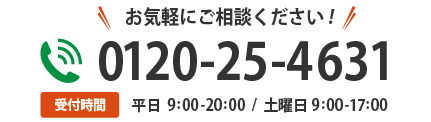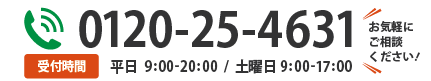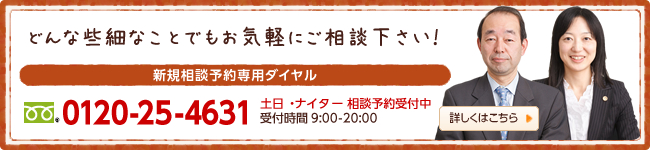相続が問題となるのは、相続人同士が遺産を巡って意見を対立させる時だけではありません。この遺産をどのように分けるべきか? そこに悩みがあるのであれば、それは相続の問題なのです。今回は、誰でも直面する可能性のある「自宅」の相続について考えます。
多くの人が経験する「自宅(実家)」の相続

今回、想定するケースは下記のようなものです。
亡くなったのは(被相続人は)Aさん。
相続人は、Aさんの配偶者であるBさん。
それから、Aさんの子Cさんも相続人です。
遺産としては、Aさんの自宅の土地建物、それからAさん名義の預貯金があります。
(なお、このケースでは寄与分や特別受益の主張は無いものとします。)
Aさん一家は仲が良く、遺産分割の話し合い自体には全く支障はありません。
しかし、BさんもCさんも、どのように遺産を分けるべきか、迷っています。
こんなケースを想定します。
実際には、もっと子ども(Cさんのきょうだい)がいたり、遺産の内容も多様だったりするかと思いますが、今回は分かりやすく、最もシンプルなケースで考えていきましょう。
民法では法定相続分というものが決められています。
今回のケースだと、BさんCさんはそれぞれ2分の1ずつが法定相続分です。
そのため、例えば、自宅の土地建物や預貯金を、すべて2分の1ずつにして相続する(土地建物は2分の1ずつの共有になる、預貯金は解約・払い戻しして2分の1ずつ取得する)ということもあり得ます。
これは確かに、もっとも素直な分け方かもしれません。
しかし、弁護士としては、ひとつリスクがあると思っております。
「不動産の共有」にはリスクがある

それは、自宅不動産が共有になっていることです。
共有の不動産は、単独所有の場合と違って、様々なことについて共有者の意思疎通・意思統一が必要となります。
例えば、自宅の建物が古くなったから取り壊して新しく家屋を建てようとしたとしても、取り壊しには共有者全員の同意が必要となります。
誰か第三者に賃貸に出して賃貸収入を得ようとした場合でも、共有者全員の同意が必要となります。
そして、自宅の土地建物全体を売却しようとする場合にも、当然、共有者全員の同意が必要となります。
したがって、不動産が共有となっていると、不動産の活用や処分の場面で、共有者全員の同意が必要となるということになります。
本件のBさんCさんは仲が良いのであるから、問題無いのではないか?と思った方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、BさんCさんがいくら仲が良いと言っても、自宅不動産の処分の方針について全くの同意見であるという保証はありませんし、今後、関係性がどのようになっていくのかは、将来のことですから「絶対」はありません。
また、仮に未来永劫仲が良かったとしましょう。
しかし、Bさんには先んじて「老い」が訪れます。
認知症で判断能力を失い、売買契約を結べなくなってしまったら?
転倒して骨折し、文字が書けなくなったり、しゃべるのが難しくなったとしたら?
医療費や介護費が必要になりBさんが売却を望んだとしても、自宅に住み続けたいCさんとの間で意見が分かれたら?
逆に思い出のある自宅を残したいと望むBさんと、売却してBさんの老後資金に充てたいCさんとの間で意見が分かれたら?
BさんCさんが合意して話を進めるということが難しくなってしまいます。
また、BさんCさんたち自身は仲が良くても、例えばBさんが老後資金のためにBさんの持ち分(2分の1)を業者に売却したところ、この買い取り業者とCさんとの間で、不動産をめぐるトラブルが勃発する、なんてことも考えられます。
このような状況になってしまうと、BさんCさんのいずれか、あるいは両方の望みが叶わないまま、不動産は塩漬け状態(現状を変更できない状態)になってしまうことにも繋がってしまいます。
これが、不動産共有のリスクです。
したがって、弁護士が遺産の分割方法についてアドバイスする際も、遺産の共有はなるべく避ける方向で助言することが多いと思います。
配偶者が相続した場合のメリットとデメリット(リスク)

共有がリスクになるということですから、今回のケースにおけるBさんかCさん、いずれかに不動産の名義を取得させるということが考えらえます。
まず、配偶者であるBさんに取得させるケースを検討してみましょう。
⑴ メリット 税制優遇制度が使える

Bさんが自宅を取得した場合は、自宅の活用や処分はBさんの思うがままですから、上記のように合意が形成できず塩漬けになるといったリスクは無くなります。
また、配偶者であるBさんが自宅不動産を単独取得することの最大のメリットは、このAさんの相続において、2つの強力な税制優遇制度を使える可能性が高いというところです。
その制度とは、「配偶者の税額の軽減」制度、それから「小規模宅地等の特例」制度です。
この記事ではざっくりとしか説明いたしませんが、「配偶者の税額の軽減」とは、配偶者が一定額(その法定相続分または1億6000万円の高い方)までの遺産を相続した場合、その部分に対する相続税はゼロ円になるという制度です。
また、「小規模宅地等の特例」とは、自宅の土地について、330平方メートルまでの部分の評価額を80%減できるという制度です。
不動産の評価額はある程度高額になりやすいですから、Bさんが自宅不動産を相続してこの2つの制度が有効に機能すれば、Aさん相続において相続税を大幅に抑えることができると思われます。
⑵ デメリット(リスク)① 認知症等

一方で、Bさんに不動産を相続させることにも、やはりリスクがあります。
まず、Bさんが存命中のリスクですが、一番大きなものはやはり高齢、認知症等のBさん自身が不動産の管理・処分ができなくなるリスクではないでしょうか。
Bさんの単独名義であっても、そのBさん自身が売買契約を結べない状態であれば、不動産は売却できません。
そのような状態であれば、もしくはそのような状態に至らなくとも、不動産の管理(ここでいう管理は、法律上の「管理」というより、日常的な手入れという意味での「管理」です。)が難しいということもあると思います。
雑草が伸びている、落ち葉が堆積している、動物や虫の住処になっている、壊れた雨どいが放置されて雨水が隣家に流れ込んでいる、庭木が道路へせり出している等々、近隣住民や交通への悪影響があるということもあるかもしれません。
しかし、当のBさんが不動産について管理や処分ができなければ、根本的な解決に至ることは難しいでしょう。
ちなみに、認知症等により判断能力を失ったという場合は、成年後見人を選任するよう家庭裁判所に申し立てを行って、成年後見人に適切な管理ないし処分をしてもらうという手立てがあります。
したがって、いざというときには成年後見人を立てるという考えでBさんが自宅不動産を相続する、ということはあり得ると思われます。
⑶ デメリット(リスク)② 二次相続

もうひとつのリスクが、「二次相続」のリスクです。
二次相続とはふたつめの相続ということですが、今回のケースでいえば、Aさんが亡くなったことによるAさん相続が一次相続(ひとつめの相続)、その後、Bさんが亡くなれば、Bさん相続が二次相続(ふたつめの相続)となります。
なぜ一次、二次と数えるかというと、今回のケースでいえば、Bさんは、Aさんの遺産を受け継いだ後に亡くなるため、事実上、Aさんの遺産が、Aさん相続→Bさん相続と2回、相続に関わることになるからです。
例えば、Aさんが亡くなり、遺産分割をしてBさんが自宅不動産を相続した直後に、Bさんが亡くなったとしましょう。
そうすると、Bさんの遺産は、Bさん固有の財産に加えて、Aさんから相続した自宅不動産(預貯金もあれば預貯金も)も含まれることになります。
これらが総額でどの程度の評価額になるかは実際の事案次第ですが、自宅不動産がある以上、ある程度まとまった金額になることが予想されます。
遺産の額に比例して、相続税も大きくなることが考えられます。
そして、最大のポイントは、Bさんが自宅不動産を相続した場合のメリットであった税制優遇制度が、Bさんが亡くなってCさんが相続する際には使えない可能性が高いというところにあります。
まず、CさんはBさんの子であり配偶者ではありませんから、「配偶者の税額の軽減」制度は使えません。
それから「小規模宅地等の特例」制度については、これも配偶者ではないため、基本的にはCさんがBさんと自宅不動産に同居していた場合しか使えません。
例えばCさんが独立して他に居を構えていたり、結婚して実家を出ていたような場合には、使えない可能性が高いと思われます。
そうすると、相続税を減らせる制度が使えず、思いがけず高額な相続税を支払う必要が出てくるかもしれません。
実際の事案でこういった税制優遇制度が使えるかどうかは税理士への相談が必要と思われますし、計算の結果、相続税がかからない(もしくはそれほど高額でない)ということも考えらえます。
しかしながら、こういった「二次相続」のリスクもあるということも見据えて、誰を自宅不動産の相続人にするか、検討する必要があります。
子が相続した場合のメリットとデメリット(リスク)

配偶者が相続した場合には上記のようなリスクがあるということですから、今度は子であるCさんに取得させるケースを検討してみましょう。
⑴ デメリット(リスク) 税制優遇制度が使えない

先にリスクについて解説します。
これは配偶者が相続する場合のメリットと裏表の関係なのですが、子であるCさんが不動産を相続する場合、Cさんは「配偶者の税額の軽減」制度は使えません。それから、自宅でAさんと同居していなければ「小規模宅地等の特例」制度も使えない可能性があります。
したがって、Aさん相続におけるCさんの相続税負担が(比較すると)重くなるということが考えられます。
⑵ メリット① 二次相続は悩まなくてよい

その代わり、上記で出てきた二次相続の悩みはだいぶ減ることになります。
Bさんには最低限の預貯金だけ相続させ、あとは自宅不動産も含めてCさんが相続するとすれば、Bさんが亡くなった際のBさん遺産総額が抑えられるため、Bさん相続における相続税が比較的安く済む可能性があります。
また、BさんがAさんの預貯金を多く相続し、あまり使わないまま亡くなったということであれば、Bさん相続(二次相続)における相続税の負担はやや重くなる可能性はありますが、不動産を相続させた場合と比べればましということはあるように思います(もちろん、実際の事案により計算はことなります。)。
それから、やや細かいことではありますが、いったんBさんに相続させてしまうと、相続登記上は、Aさん→Bさん→Cさんと2回の登記が必要となりますが、Cさんが相続するのであれば、Aさん→Cさんの1回のみの登記で済みますので、費用や手間の削減につながります。
⑶ メリット② 認知症等のリスクは低い

それから、子であるCさんは、原則的には親であるBさんよりも若く、認知症等判断能力を失ったり、実際に管理することができなくなるようなリスクは比較的少ないと言えるでしょう。
そのため、いざ不動産を売却しようとしたときに成年後見人が必要になるというようなこともなく、スムーズに売却できる可能性が高いように思われます。
例えば、Bさんの老後資金のために自宅不動産の売却が必要になったとしても、Cさんの独断で売却が可能ですから、「将来Bさんのために売却する」ということが方針として決まっていたとしても、Cさんが相続するということは十分に考えられます。
結局、どっちが相続するべきなの?

上記のとおり、それぞれの選択肢のメリットとデメリット(リスク)を検討してきました。
どちらも一長一短があり、完璧な選択肢はありません。
それに、実際の事案では、親子の年齢、健康状況、今後の人生設計、遺産の構成、遺産総額、子の同居の有無等、さまざまな事情を総合的に考慮して、さらには相続税のシミュレーションもしながら判断しなければ、結論は出ないと言えると思われます。
それでも強いて一般論を述べるとするならば、
①安易な「共有」という結論は避けるべき
②一次相続の相続税等に問題が無いなら「子」が相続する方がメリットが多い
というところでしょうか。
この辺りは、もちろん事案にもよると思いますが、弁護士それぞれ、税理士それぞれのアドバイスがあると思います。
ぜひ、様々な観点からアドバイスをもらいながら、ご自身の事案にとって最善の方法が何か、検討してみてください。
そしてその際にはぜひ、弊所の相続チームの弁護士へご相談ください。お客様に寄り添いお話を伺い、よりよい解決方法を一緒に考えたいと思います。
グリーンリーフ法律事務所は、設立以来35年以上の実績があり、18名の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。
また、各分野について専門チームを設けており、ご依頼を受けた場合は、専門チームの弁護士が担当します。まずは、一度お気軽にご相談ください。