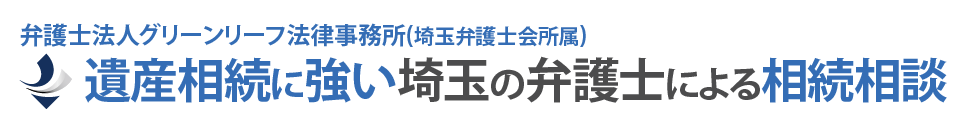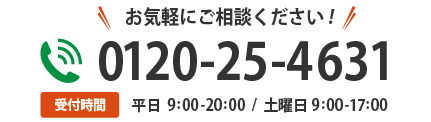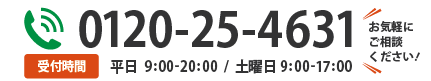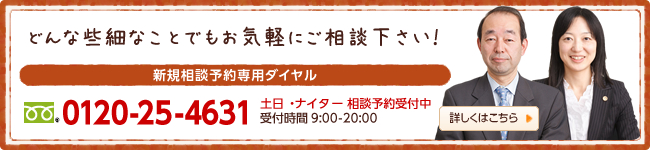近年、株式投資を始める人が増えた影響もあり、相続財産の中に株式が存在するケースが増えています。株式ももちろん、相続の対象財産です。本稿では、株式の相続手続きについて、上場株式と非上場株式に分けて、弁護士が解説します。
相続財産の中の株式
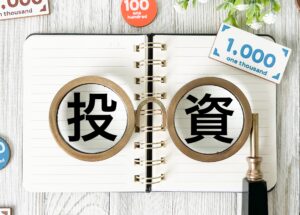
近年、政府が「貯蓄から投資へ」と謳い、少額非課税投資制度を拡充したこともあり、個人で株式投資をする方が増えています。
それに伴い、被相続人が残した相続財産の中に株式が存在するケースも増えています。
株式も財産ですから、遺言がなければ、他の相続財産とともに遺産分割の対象となります。
しかし、こと株式に関しては、不動産や預貯金などの財産と比べて馴染みが薄く、どのように取り扱っていけばよいのか戸惑う相続人も多いようです。
株式発見の端緒

生前に被相続人から株式を持っていることを聞いていても、どの証券会社にどのような銘柄の株式を預けているのかまで、相続人が把握していることは稀だと思います。
そこで、被相続人宛てに証券会社からの通知書や取引状況報告書などが届いていないか、確認してみて下さい。
書類が見つからなくても、慌てる必要はありません。
生前に被相続人から「株をやっている」と聞いていて、株式を持っている可能性があるのであれば、証券保管振替機構(「ほふり」)に問い合わせてみましょう。開示請求を行えば、被相続人がどの証券会社と取引があったか開示してもらえます。
株式の相続手続きをせずに放置した場合

さて、株式の存在が明らかになったとして、仮に、「何となく面倒臭いから」と相続手続きをせずにそのまま放置するとどうなるでしょうか。
株式の相続手続きが完了しない間は、その株式は相続人全員で共有(正確には「準共有」)している状態のままです。
このため、配当金も、その都度、相続人全員で法定相続分に従って分配する必要がありますし、株主総会で議決権を行使したい場合は、相続人のうち1人を権利行使者として定めて、会社に通知しなければなりません。
このように、株式の共有状態を続けることはそれこそ「面倒臭い」と言えますので、早めに相続手続きを完了させる方がよいでしょう。
株式の相続手続き

それでは、きちんと株式の相続手続きを行うとして、具体的にはどのように進めていけばよいのでしょうか。
以下、「上場株式」と「非上場株式」に分けて説明していきます。
上場株式の相続手続き
上場株式は、東京証券取引所など各取引所で売買する資格を与えられた、つまり、市場流通性のある株式です。
被相続人が「株取引をしている」「株で利益が出ている」等と話していたのであれば、それは上場株式のことを指していることが多いです。
ステップ① 証券会社に連絡を入れる

まずは、被相続人が株式を預けていた証券会社へ連絡をして、名義人である被相続人が死亡したことを知らせます。
そのうえで、相続人に名義変更したい旨も伝えましょう。
後日、証券会社から、申請書など手続きに必要となる書類一式が送られてきます。
ステップ② 遺産分割協議をととのえる

遺言でどの株式を誰が取得するのか指定されている場合を除き、相続人のうち誰がどの株式を取得するのか、遺産分割協議を行って決めなければなりません。
株式の評価
分割協議を行う際、株式の評価額が決まらなければ、各人の取り分を決めることもできません。
特に、株式は日々刻々と値動きがありますので、評価時(どの時点の値をもって評価するのか)が重要になってきます。
この点、遺産分割を行う際の遺産の評価時は、原則として「遺産分割時」となります。
家庭裁判所における実務では、「遺産分割時に最も近接した時点での最終価格(終値)」によって評価する取扱いとなっています。
終値は、日刊新聞や東京証券取引所などのホームページなどで調べることができますし、インターネットの「Yahoo!ファイナンス」にアクセスすると、銘柄を指定して簡単に確認することができます。
なお、相続人全員の合意があれば、上記と異なる評価方法、例えば、相続が発生した月の最終価格(終値)の月平均価格、などとすることも自由です。
株式の分割方法
株式の評価額が決まったら、次は、株式をどのように分けるかを決めていきます。
【株式をそのまま取得する(現物分割)】
相続人のうちの誰かが、株式をそのまま相続する方法です。
例えば、
・全ての株式を妻が取得する
・●●の株式は全て長男が、■■の株式は全て長女が取得する
・●●の株式のうち200株は長男が、150株を次男が取得する
といった形で、株式を株式のまま受け継ぐやり方です。
なお、株式を取得した相続人が、他の取得財産と合わせて自己の法定相続分を超える価額を取得することになる場合は、超過分につき、他の相続人に対し代償金を支払うことにして、相続人間の公平を図ります。
【株式を売却して売却代金を分ける(換価分割)】
株式をいったん売却して、売却代金を相続人間で分配する方法です。
相続人の誰も投資や株式に関心がない場合には、この方法が良いかもしれません。
売却代金の分配の仕方は、一般的には法定相続分の割合によることになりますが、相続人間の合意で自由に割合を定めても構いません。
ステップ③ 相続人の証券口座を用意する

株式を相続するときには、被相続人名義から相続人名義に書き換えた株式を相続人の証券口座に振り替えてもらう必要があります。
このため、必ず、相続人名義の証券口座が必要となります。
証券口座を持っていない人は、新たに証券口座を開設して下さい。
ステップ④ 必要書類を揃えて証券会社に送る

遺産分割協議がととのい、証券口座の用意もできたら、遺産分割協議書と口座振替の申請書に、証券会社から指示された必要書類を揃えて、証券会社に郵送します。
多くの場合、相続関係が分かる戸籍謄本、住民票や本人確認書類が必要となります。
ここまで来れば、株式の相続手続きは完了です。
証券会社の方で、被相続人名義の株式を相続人名義に変更したうえで、相続人名義の証券口座へと振り替えてもらえます。
以降は、その相続人が株主ということになりますので、株主総会の通知なども全て相続人に届くようになりますし、配当金も全額受け取れるようになります。
非上場株式の相続手続き

以上は、市場流通性のある上場株式の話でしたが、これに対し、非上場株式(証券取引所には公開されておらず、一般に流通していない株式)の場合は、相続手続きがかなり異なります。
非上場株式が問題になるのは、被相続人が会社を経営している場合や、親族や知人の会社に出資している場合などです。
株式の評価
上場株式と異なり、市場における相場がありませんので、非上場株式の評価は難しい問題です。
家庭裁判所における実務では、会社法上の株式買取請求の際の価格算定方法(純資産方式、配当還元方式、類似業務比準方式、収益還元方式、混合方式など)や税務上の評価基準(類似業種比準方式、純資産方式、配当還元方式など)を参考に評価していきます。
その結果、会社の規模や業績によっては、無価値(0円)と評価されることもあります。
株式の分割方法
非上場株式の場合は、亡くなった親の会社の経営を引き継ぐ相続人が、全株式を取得する例が多いです。
株式を分散相続させてしまうと、今後の会社の経営・存続に影響が出かねないためです。
この場合、会社の経営にタッチしていない相続人から異論が出ることも少ないでしょう。
グリーンリーフ法律事務所は、設立以来35年以上の実績があり、18名の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。
また、各分野について専門チームを設けており、ご依頼を受けた場合は、専門チームの弁護士が担当します。まずは、一度お気軽にご相談ください。