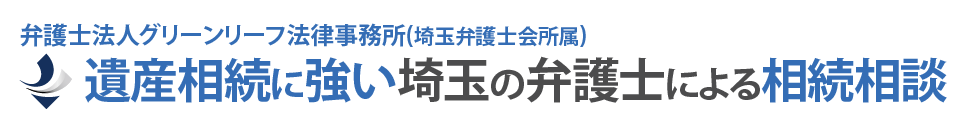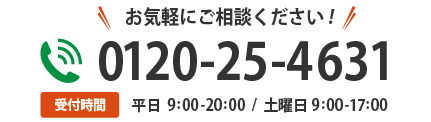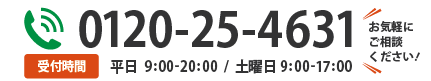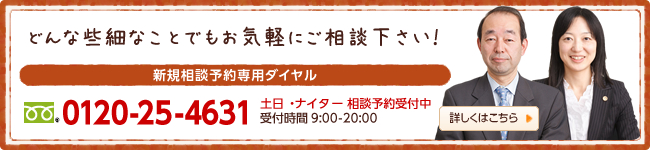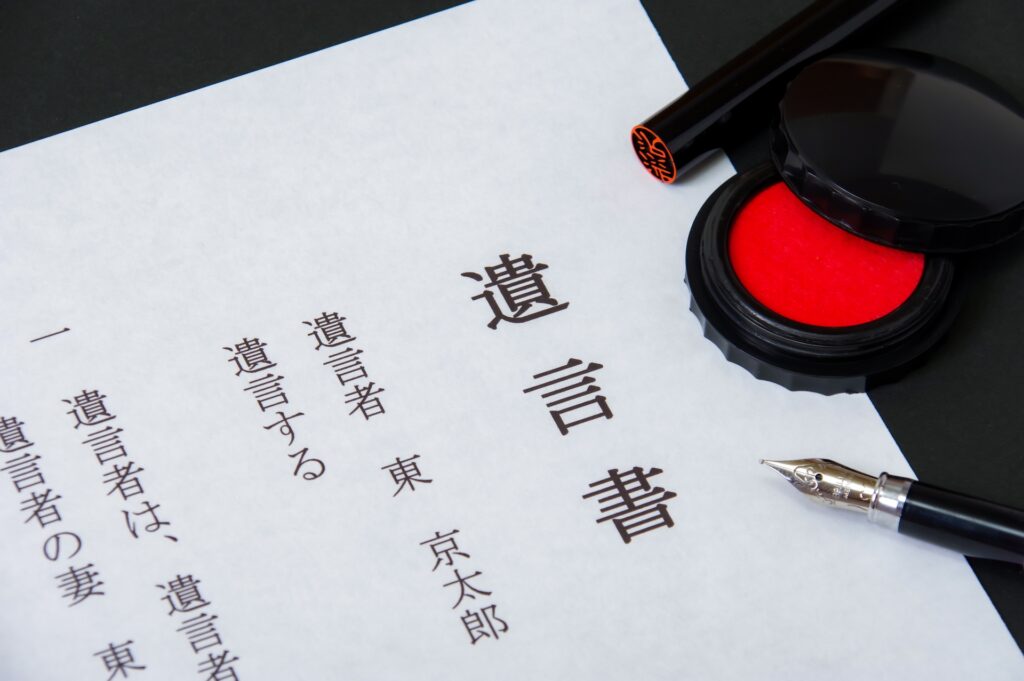
遺言書と遺書、遺言(いごん)と遺言(ゆいごん)。似ているこれらの言葉ですが、相続という場面ではいずれも大切な役割を担います。この記事では、これらの定義や法的効果の違いを解説した上で、それぞれどのような意義があるのかについて解説します。
「遺言」は故人のメッセージ

人が亡くなる際に、口頭やお手紙などの何らかの形で、見送る人々にメッセージが残されることがあります。
一般に、遺言(ゆいごん)や遺書などと呼ばれるものです。
一方で、民法は「遺言(いごん)」という制度を設けています。
これは、法的な効果をもつ、れっきとした法律行為です。
意外に思われるかもしれませんが、法律行為という意味では、家や車を買う(売買契約)とか、契約を解除するとか、そういった行為と同じということになります。
同じ漢字で「遺言」と書いたり、「遺書・遺言書」などのように字面が似ていたりして、これらの違いについて上手く説明できないという方も多いと思いますし、それは仕方のないこととも思われます。
というのも、現実では、誤用の他にも、分かりやすいようにこれらの言葉をあえて混ぜて使っていたり、例えば「遺書」と書かれている書面が実際には「遺言書」として機能したり、その逆のパターンがあったりなど、その境界があいまいになっているからです。
この記事では、一般的な意味での「遺言(ゆいごん)」と民法上の「遺言(いごん)」の違いを解説した上で、故人のメッセージに直面した我々が、どのように受け止めれば良いか考えていきたいと思います。
「ゆいごん」と「いごん」は何が違う?

※この記事では、「遺言(ゆいごん)」を一般的な意味での故人の遺したメッセージや意思表明のこと、「遺言(いごん)」のことを民法上の制度のこと、として使い分けます。
さて、「遺言(ゆいごん)」というのは、一般に、故人の遺したメッセージや意思表明のことを指すかと思います。
例えば、亡くなる間際に見守る家族に対して「あとのことは頼む」とお願いしたり、「遺書」と題した手紙を書き「先立つ不孝をお許しください。今までありがとうございました。」などと伝えることなども、この「遺言(ゆいごん)」に当たると考えられます。お葬式は身内だけで質素にしてほしい、お骨は散骨してほしい、などといった要望として伝えられることもありますね。
このとおり、「遺言(ゆいごん)」の場合は、そのメッセージの内容やメッセージの残し方・形式は自由となっています。
そのため、必ずしも法律的な効果をもつものではなく、故人と遺された人々の、いわばコミュニケーションの一環ということになります。
一方で、民法上の「遺言(いごん)」は、上記にも出てきたとおり、法律的な効果をもたらす法律行為です。
すなわち、民法で定められた方式に従って、遺言ができるとされている項目について意思表示を行うことで、その法的効果を実現するという性質の行為ということになります。
代表的な内容としては、遺産の分配方法の指定などですね。
逆に言えば、「遺言(いごん)」には限界があります。
どんな内容でも遺言(いごん)として遺せるわけではありませんし、遺言(いごん)として認められている範囲の外のことについてメッセージを遺したとしても、それは遺言(いごん)としての法的効果を持ちません。
そうとはいえ、遺言(いごん)は、生前の様々な事情を勘案して、故人が「こうしたい」と思った結果の表れという側面があります。
例えば、生前にとてもよく面倒を見てくれた人物に対して報いたいと思って、「遺産は○○に遺贈する」などと遺言したとすれば、それは感謝の気持ちの表れになるでしょう。
「遺産は子どもたちで等分するように」と遺言されていれば、故人としては、遺された子たちが仲良くすることを願っているという風にも受け取れます。
このように、遺言(いごん)は法律行為であり、故人の考えや感情を反映した故人からのメッセージでもあるとも言えるのです。
遺書が「遺言書」として機能するケース

上記で、遺言(ゆいごん)は形式や内容が自由ですが、遺言(いごん)は形式や内容に法律上の縛りがあるという話をしました。
遺言(いごん)には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言という3つの種類があるのですが、このうち遺言(ゆいごん)との異同が問題となるのは、主として「自筆証書遺言」かと思われます。
「自筆証書遺言」とは、字の如く、自分で筆記して作成する遺言(いごん)・遺言書のことです。
「自筆証書遺言」として成立するための主な要件(民法968条)は以下のとおりです。
① 全文・日付・氏名を自書すること
② 押印をすること
なお、この内①については、財産目録をつける場合における目録についてはパソコン書きなど自書に依らなくても良いことになりましたが、本文の方については、やはり全文自書がもとめられています。
上記の形式を満たしていれば、例えば便箋やはがき、ルーズリーフに書いてあったとしても、また、冒頭に「遺言書」と書いておらず「愛する家族たちへ」などと書いてあったとしても(この場合は内容にもよると思いますが)、遺言(いごん)として有効になります。
「遺書」というタイトルでも結構です。
上記の形式を満たし、内容が遺言(いごん)に相当する内容であれば、それは遺言(遺言)の書かれた「遺言書」となるわけです。
逆に、例えば署名押印が抜けているなど、上記の要件を欠いていた場合には、いくら題名が「遺言書」と書かれ、内容も遺言(いごん)として相当なものであったとしても、法律上有効な遺言(いごん)としては扱われません。
例えば具体的な遺産配分が書かれているメモが見つかったとしても、日付・氏名・押印が無ければ自筆証書遺言としては無効となります。
ちなみに、遺言(いごん)が書かれた文書を「遺言書」、遺言(ゆいごん)が書かれた文書を「遺書」と呼び分けることが多いかと思いますが、冒頭でもお話したとおり、実際は文脈で判断する必要があるように思います。
遺言書が「遺書」として機能するケース

一方で、遺言書が一般的な意味での「遺書」として、すなわち遺言(ゆいごん)が表記された書面として、機能するケースがあります。
もちろん、上記でもお伝えしたとおり、財産をこのように分けて欲しいという遺言(いごん)の内容から、被相続人の心情を推測するということも、ある意味では「遺書」としての機能の一部かもしれません。
しかしながら、もっと明確なものとして、「付言事項」というものがあります。
付言事項とは、遺言書の中で(多くの場合は遺言書の最後に)、法的な効力を及ぼさない単なるメッセージや説明、希望などを記載した部分になります。
例えば、「長男に自宅を相続させる」という遺言(いごん)を遺した際に、その遺言書の最後に「長男には家業を継いでもらったので、今のまま自宅に住み続け、家業を続けて欲しい。」などと、遺言の理由や背景について記載することができます。これが付言事項です。
ほかにも、「○○は生前甲斐甲斐しく介護をしてくれるなど尽くしてくれた。感謝の気持ちとして○○を受け取って欲しい。」とか、「争いを起こさず、どうか仲良く遺産を分け合ってください」などと、感謝や要望を記載することもあります。
繰り返しになりますが、付言事項は法的効果を持ちません。
すなわち、遺言(ゆいごん)としての機能を果たす部分であるということです。
このように、遺言書の中にも、遺言(ゆいごん)・遺書としての部分が存在するということがあります。
法的効果が無いのになぜ付言事項をつけるのか、と思われる方もいるかもしれません。
しかしながら、相続問題というのは、どうしても感情的な面と切り離せないところがあります。
いざ相続に向き合うことになった相続人にとって、ただ「こう分けなさい」と遺言で指定されるよりも、「こういう理由があるので」と被相続人からのメッセージとして説明される方が、受け入れやすいということもあると思います(逆のパターンも無いではないですが…)。
弁護士としては、強制はしませんが、特に法定相続分から乖離した遺言(いごん)を遺したいという場合には、付言事項をつけることをおすすめしています。
「遺書」は遺産分割に効果無し?

上記のような説明をすると、「遺書は意味がないのでは?」と感じる方も出てくることでしょう。
確かに、遺言(いごん)の形式的な要件を満たさない遺書の場合、遺言(いごん)としては扱えませんから、法的な効果はありません。
しかしながら、前述の付言事項がそうだったように、遺言(ゆいごん)は相続人にとって相続問題解決の指針、道しるべになることがあります。
例えば遺産分割を行う際には法定相続分で分けることが原則ではありますが、相続人全員の合意によって、遺産の分け方に偏りを持たせることもできます。
その偏りの指針として、「○○に家を守って欲しい」とか「○○にはこういう負担をかけたから、その分、よく話し合って補うように」などと遺言(ゆいごん)が残っていれば、相続人同士の話し合いや感情の整理に影響を与える可能性があります。
法的効果を持つ遺言(いごん)ではありませんが、相続人らが被相続人の意思を汲み取った結果、遺言(ゆいごん)どおりの遺産分割を行うということもあり得るということです。
また、例えば別に遺言書があり、その解釈が問題となっている場合に、遺言(ゆいごん)の内容を参考に遺言書を解釈するという実務的な使われ方もあり得ます。
このように、単に法的効果が無いからといって、遺産分割という法的な場面で、遺書が全くの無意味ということにはならないと考えられます。
ただし、繰り返しになりますが、遺言(ゆいごん)・遺書には法的効果はありませんから、「遺産をこう分けたい」というご希望がある場合には、法的効果のある遺言(いごん)を確実に残すことを第一に考えて頂ければと思います。
まとめ

いかがだったでしょうか。
「いごん」と「ゆいごん」、遺言書と遺書は、上記のとおりの差がありますが、現実にはその境界は(ある意味で)曖昧になっているものと思われます。
ただし、法的効果を持つ遺言(いごん)については、その要件が定められており、これを欠く場合には法律上の効果を持たせることができません。
そのため、遺産の分け方について要望がある場合には、法的に有効な遺言(いごん)を作成することを強くおすすめいたします。
ただし、遺言(ゆいごん)や遺書は、故人と遺された人々との間の大事なコミュニケーションのひとつです。法的効果が無いという理由でこれを無意味と断じることはできないと思います。
法的な意味を持つ遺言(いごん)、心情的な意味を持つ遺言(ゆいごん)。
これらはいずれも相続にとって欠かせない、尊く、大事なメッセージです。
遺言(いごん)のみならず、感謝、後悔、希望、期待などの率直なお気持ちを、ぜひ遺書や付言事項というかたちでお伝えしてみてはいかがでしょうか。
グリーンリーフ法律事務所は、設立以来35年以上の実績があり、18名の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。
また、各分野について専門チームを設けており、ご依頼を受けた場合は、専門チームの弁護士が担当します。まずは、一度お気軽にご相談ください。