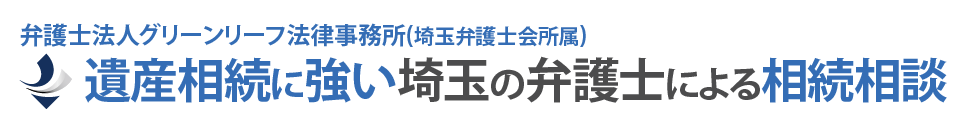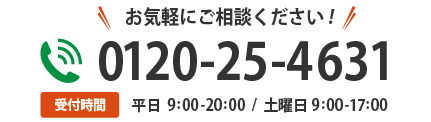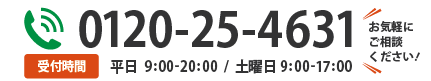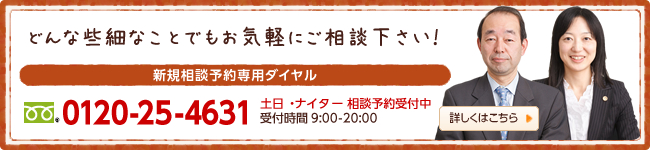被相続人が孤独死した場合は、相続人の確定や相続財産の把握、不動産の処分や賃貸物件の明渡しに困難が生じることが多いものです。本稿では、孤独死の場合に遺族が直面するこれらの問題について、それぞれの注意点を弁護士が解説していきます。
近年増加している孤独死

孤独死とは、一人暮らしの方が、誰にも看取られることなく自宅で亡くなることを意味します。
法律用語ではなく、一般的に広く使われるようになった言葉です。
死因は、病死のこともあれば、自然死のこともあります。
近年、孤独死は増加しています。
警察庁の統計によると、2024年に孤独死した人の数は7万6020人にのぼり、うち65歳以上が7割以上を占めているとのことです。
また、死亡してから発見されるまでの経過日数は、1日以内が2万8756人と最も多かった一方で、31日以上経過していた人が6945人、1年以上経ってから見つかった人が253人など、死後長期間が経過してから発見されるケースも少なくありません。
親族が孤独死したら相続人はどうすべきか?

ある日突然、警察から「あなたの親族が孤独死の状態で発見されました」との連絡が―――。
その親族とは長年連絡をとっておらず、生前の近況も全く分かりません。
このような状況でも、あなたがその人の相続人であれば、相続問題は容赦なく降りかかってきます。
残された相続人は、どのような点に気を付けて相続問題を乗り切って行けばよいのでしょうか。
孤独死と相続の注意点① 相続人の確定に時間がかかる
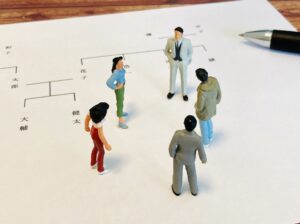
遺産分割協議は相続人全員で行う必要があり、一人でも相続人が欠けていれば、せっかくととのった協議も無効になってしまいます。
そこで、遺産分割を行うためには、何よりもまず、相続人を漏れなく把握することが重要なのですが、孤独死の場合、この相続人の確定に時間がかかることが多いです。
孤独死した方はそもそも親族との付き合いが希薄なケースが多いので、死亡の連絡を受けた方が、その方の配偶者や子供の有無をよく知らないことも珍しくありません。
また、疎遠になっている間に、孤独死した方は、近しい親族の誰も知らない、新たな家族関係を築いている可能性もあります。
さらに、警察から連絡を受けたからといって、連絡を受けた方が相続人にあたるとも限りません。
誰が相続人になるかは、孤独死した方の出生から死亡までの全ての戸籍謄本を取り寄せて、正確な親族関係を把握したうえで確定する必要があります。
死亡から出生まで、遡って戸籍を辿るしかないのですが、転籍を繰り返しているような方だと順番に戸籍を追っていくだけでも大変な作業になります。
孤独死と相続の注意点② 相続財産の把握に伴う困難
遺産分割を行うためには、相続人を正確に確定するほか、対象となる相続財産を把握する必要があります。
しかし、疎遠になっていた親族が孤独死した場合は、その方の財産について知っている者がほとんどおらず、近しい親族が亡くなった場合に比べて、相続財産の把握が困難であることが多いのです。
持ち家で亡くなった場合は、不動産の所在は明らかですが(ただし、自宅以外の不動産の有無については留意する必要あり)、預貯金、株式、生命保険、負債の有無などは、容易に把握できない状態かもしれません。
孤独死した方の部屋の片付けや遺品整理をする中で、
■通帳やキャッシュカード、銀行の利用明細がないか
■証券会社や保険会社からの郵便物が届いていないか
■金融機関や貸金業者から借金の督促状が届いていないか
■届いている固定資産納税通知書に把握していない不動産が記載されていないか
等を確認し、相続財産を探索していくことになります。
孤独死と相続の注意点③ 不動産の処分に伴う困難

孤独死した方が自宅(持ち家)で亡くなっていた場合、その自宅不動産を売却処分しようとしても、なかなか買い手が見つからないか、あるいは、一般の市場価格より廉価で売却しなければならないかもしれません。
特に、亡くなってから発見されるまで長期間放置されてしまったケースでは、特殊清掃やリフォームなどを実施して物件内部を綺麗にしたとしても、買い手に敬遠される傾向があります。
だからといって、孤独死が発生した事実を隠して売却すれば、後々、買主との間でトラブルに発展する可能性があります。
仲介を依頼する不動産会社には、きちんと孤独死が発生した事実を伝えておきましょう。
建物が古い場合には、思い切って建物を解体し、更地の状態にして土地だけを売りに出すという方法もあります(その場合でも告知義務は別途問題になります)。
いずれにせよ、孤独死の発生した不動産を相続する場合には、その後の売却処分には困難が伴うことを、事前に覚悟しておく必要があると言えます。
孤独死と相続の注意点④ 賃貸物件の原状回復に伴う困難

孤独死した方が賃貸物件で亡くなっていた場合、賃貸人から多額の原状回復費用や損害賠償を請求される可能性があります。
賃貸借契約は賃借人の死亡によって当然に終了するものではありませんが、大抵の場合、相続人は継続を望みませんから、賃貸物件からの退去、すなわち明渡しと原状回復が必要となります。
この点、孤独死が発生したケースでは、原状回復費用が通常の場合より高額になる恐れがあります。特に、死亡後発見までに長期間を要した場合、遺体の腐敗による汚損や臭気を除去するために特殊清掃やリフォームが必要となりますので、その分、原状回復費用は高額になりがちです。
また、孤独死の発見が遅れて長期間放置された場合などはいわゆる「事故物件」となり、賃貸人は、次の募集をかける際にその事実を告知せざるを得ません。
その結果、なかなか次の借り手が見つからない、見つかったとして通常の賃料より低い賃料でしか契約できないなど、賃貸人に損害が発生する場合には、相続人が損害賠償を請求される可能性があります。
相続放棄も検討を
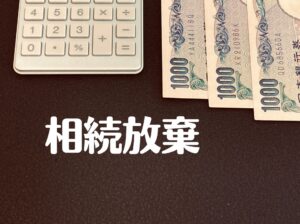
以上のとおり、孤独死が発生した場合の相続は、一筋縄ではいかない様々な難点を抱えています。
そこで、相続放棄をして、そもそも孤独死した方の相続人にならない、という選択肢もあり得ます。
もちろん、孤独死した方に、多額の資産があることが明らかであって、相続することのメリットの方が断然大きいという場合は別です。
しかし、そうでない場合は、残された資産と負債や負担を天秤にかけ、相続するかどうかを慎重に見極めた方がよいでしょう。
相続放棄は、原則として、孤独死が発生した事実及び自分が相続人になることを知った時から3か月以内に、家庭裁判所に申述して行う必要があります。
孤独死の場合は、相続人の確定や相続財産の把握にただでさえ時間がかかりますので、どうしようか決めかねているうちに、3か月などあっという間に経ってしまうかもしれません。
その場合は、3か月の期限を延長してもらうよう家庭裁判所に申し立てる方法もあります。
特に、賃貸物件で孤独死が発生した場合は、先に見たとおり、賃貸人から多額の原状回復費用や損害賠償を請求される恐れがあります。
相続放棄をすれば、プラスの財産も引き継げない代わりに、そうした支払義務からも逃れることができますので、検討に値すると言えるでしょう。
グリーンリーフ法律事務所は、設立以来35年以上の実績があり、18名の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。
また、各分野について専門チームを設けており、ご依頼を受けた場合は、専門チームの弁護士が担当します。まずは、一度お気軽にご相談ください。