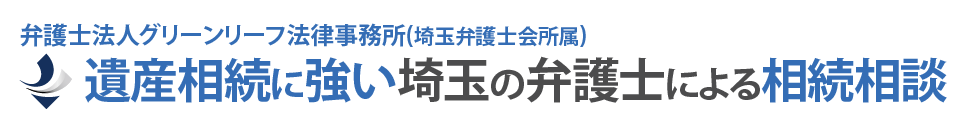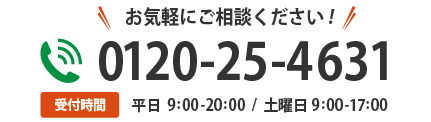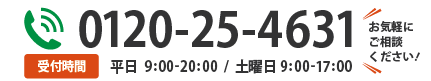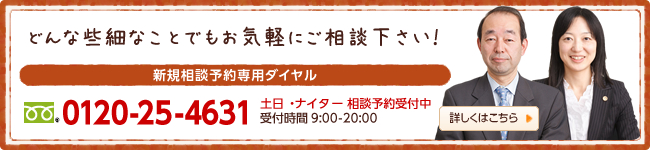紛争の内容
被相続人A氏の相続人は、兄弟であるBさん、C氏、D氏の3名でしたが、C氏・D氏は異母兄弟であり、生前から全く付き合いのない状態でした。
A氏の遺産は、実家不動産のほか、1000万円程度の預貯金がありました。
Bさんは、C氏・D氏に対し、A氏が亡くなったことと、A氏の遺産分けをしたい旨を書いた手紙を何度も送りましたが、受領はあるものの、2人からは何の応答もありませんでした。
行き詰ってしまったBさんからご依頼を受け、弁護士や裁判所が間に入れば事態が動くかもしれないと期待して、遺産分割調停を申し立てることにしました。
交渉・調停・訴訟等の経過
家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てるあたり、弁護士から別途、手続きへの協力を願う旨の手紙を送りました。
すると、C氏からは、第1回調停期日の前に、裁判所に宛てて、「遺産は全部Bが取得してよいが、自分の取り分に相当するお金は支払って欲しいです」と記載された回答書が送られてきました。
調停委員とも相談し、明らかになったC氏の要望をもとにした調停条項案を弁護士が作成。
第2回調停期日までの間に、その調停条項案をC氏・D氏に送り、C氏に対しては「このような内容で間違いないか確認するとともに、振込口座の情報を教えて下さい」とお願いし、D氏に対しては、「C氏からは希望の表明があってこのような条項案を作ったが、D氏の希望も是非聞かせて欲しい」とお願いしました。
すると、C氏からは振込口座の情報を記載した回答書が、D氏からは「自分は何も相続したくありません」と書かれた回答書が、それぞれ返ってきました。
こうして両者の意向が確認できたため、弁護士作成の調停条項案のとおりで進めることとし、相手方ら不出頭でも解決できるよう、裁判所が調停に代わる決定を出すことになりました。
本事例の結末
遺産分割調停成立(調停に代わる決定が確定)
内容は、「A氏の遺産は全てBさんが取得し、Bさんは代償金としてC氏に相当額を支払う。D氏は何も取得しない」というもの。
本事例に学ぶこと
当事者が話し合いをしようと連絡をしても何の応答もなかった相手方らが、弁護士や裁判所が間に入った途端に応答してくれるようになることは往々にしてあり、本件はその好例です。
予想したよりも早期に解決することができ、Bさんにも喜んでいただくことができました。
弁護士 田中 智美