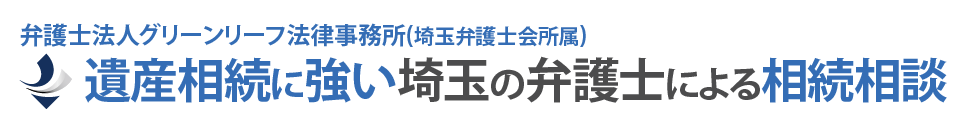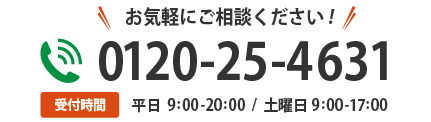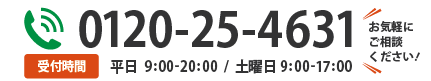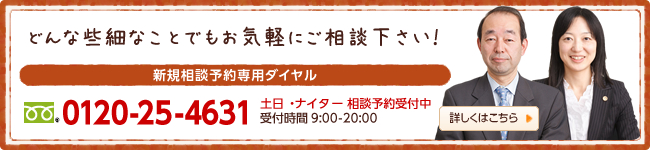紛争の内容
ご依頼者様は代々続く農家の長男でしたが、すでに独立しており、家業である農業はご両親と同居していた三男家族が継いでいました。
しかしながら、お父様・お母様が相次いで亡くなり、相続が発生しました。
お父様・お母様は公正証書遺言を遺しており、これによれば、田畑や賃貸アパートを含む遺産の大半について三男が相続するとされ、家業を継がなかったご依頼者様と二男には多少の預貯金のみが取り分として指定されていました。
三男と比べたときにご自身の相続できる金額があまりにも少なかったため、ご依頼者様は弊所にご相談にいらっしゃいました。
交渉・調停・訴訟等の経過
このように遺言や生前贈与によって相続人間に大きな不公平が生じている場合には、遺留分の侵害がないか検討する必要があります。
本件では、不動産が多々あり、その評価額がいくらであるかという問題はあったものの、ご依頼者様の遺留分が侵害されていることは明白でした。
そのため、遺留分侵害額請求交渉をご依頼頂きました。
ご依頼後、速やかに遺留分侵害額を請求する旨の通知を相手方に送付しましたが、返答はありませんでした。
そのため、続けて遺留分侵害額請求調停をご依頼頂き、管轄の家庭裁判所に調停を申し立てました。
相手方は、今度はきちんと調停手続に出席し話し合いに応じてくれましたが、遺産の評価額についてなかなか合意することができず、難航しました。
しかし、調停委員を介して、不動産の評価が合意できなければ相当の費用をかけて鑑定することになること、調停で話し合いをまとめることができなければ訴訟になり、経済的にも心理的にも負担が続くことなどから、双方のためにも何とか調停をまとめられないか働きかけを続けました。
本事例の結末
そうしたところ、調停不成立となる直前で、相手方の譲歩を引き出すことができ、結果としてご依頼者様の納得できる金額で決着することができました。
その後、支払期日までに相手方から支払いがあり、本件は無事に終了となりました。
本事例に学ぶこと
本件では多数の不動産や預貯金、保険契約等があり、遺産全体の規模は数億円ともなりました。
一方で、本件のように遺産に多くの不動産が含まれる場合、その評価額によって、遺産総額が大きく変動することがあります。遺産総額が変われば、当然、遺留分も比例して変動します。
また、その他にも、生前贈与について計算に含むか含まないかという争いもあり得ます。
本件では、こういった変動し得る要素や判例・裁判例について丁寧に検討し、訴訟に移行した場合に得られるだろう経済的利益をシミュレーションいたしました。このように先の見通しを持っていたおかげで、相手方から引き出すべき譲歩のラインを見極めることができました。
遺産規模が大きい相続(遺産総額1億円以上など)や不動産が多数存在する相続については、特にこの「見通しを持つ」ということが重要となりますので、是非弁護士に一度ご相談頂ければと思います。
弁護士 野田 泰彦
弁護士 木村 綾菜